2016年10月20日
The北海道ファームでは、普段は真面目にお米を作っていますが、
時には、農家の範疇を飛び出すような作業も行います。
今回は、倉庫の修理です。
The北海道ファームでも栽培方法の展開で機械や資材が増えてきました。
そこで、敷地内に昔からある古い倉庫を直して活用しようという作業を進めています。

こんな感じの 通称D型ハウス 北海道の農家ではよくあるタイプです。
大きさ的には、6間×7間くらいです。
ただ、倉庫内の地面が土のため、地形の関係もあり
雨が降ると倉庫内に川が流れるような状態です・・・・・。
そこで今回の地面のかさ上げと作業性の向上のためにドマコンを打ちました。
「ドマコン?」の方は、読み進めていただければ、解ってきますよ。
まずは、地面の整地作業から。

斜面状になっている地面を、小型ユンボで平らに修正していきます。
6×7間のちょっとした広さの場所で最大15cm程度の高低差を
平らにならしていく作業なので、微妙な操作が要求されます。
オペレーターは、本社より出張中のお墓も立てるD社員。

地面を平らにしたら、コンクリートを流し込む際の型枠を作成していきます。
D型ハウスの束石よりやや狭く作るのがポイントです(何の?)。
さらに、コンクリの下になる砂利をダンプで搬入し、

これもユンボでならしたり、転圧機で砂利を叩き込んで地面を固めていきます。
ドマコンうちの下地作業ですね。何事も下地が大事。
ここで手を抜くと仕上がりにも影響が出てきます。
ここでユンボはS社員に交代していますね。
なお黄色いシャツの重量級H社員は、転圧機を使わずに
得意の四股を踏めば地面が固まりそう・・・。
数日かけて、下地が整ったらいよいよコンクリうちの開始です。

今回は、ミキサー車+ポンプ車で大工事のようになっています。
後ろの青いミキサー車からコンクロートが下りてきて、
手前の白いポンプ車で建物の奥までコンクリートが送り込まれます。

で、コンクリートを流してもらいながら、生のコンクリートをならしていきます。

今回は、コンクリートの中に通称メッシュと言われる金網を埋め込んで
コンクリの強度を高める方法を取りました。
自家製、自家使用なので鉄筋を組まない簡易使用でやってみました。

約6×7間なのでざっと20坪程度、結構広いのでコンクリートをならすのも大変でした。
後は、数日おいてのコンクリートが固まれば、見事完成ですが
その結果は、数日後という事になります。完成披露はお楽しみにという事で。
「このくらいになると、もう農家の仕事じゃないよね」という素直な感想が出る仕事でした。
ここ数年、The北海道ファーム含む十全社グループが、
自分たちで、できる仕事の範囲がますます広くなってきました。
お葬式のお手伝いはもちろん、料理関係、お米の栽培、
土木建築的な仕事に お花関係も切り花から鉢花、造園、森林伐採まで。
なんだかすごいことになってきましたね。
そんな、多様な仕事ができるのでお客さんが来て
客「業者さん入れて何されるんですか?」
僕「いや、あれ自分たちで〇〇してるところ」
客「・・・・・なんでもやるんですね!」 という会話が最近ありがちです。
2016年10月20日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
田んぼでの稲刈りは、ずいぶん前に終わりましたがお米は稲刈り後に乾燥調製の作業をしないと食べられません。
稲刈りの翌日に「稲刈り終わったなら、新米をたべたい」と言ってくる方がいますが、基本無理です。
農家以外の方には 意外に知られていない所です。
で、その乾燥調整作業については、The北海道ファームのホームページのこの部分を参照してください
おいしいお米をお届けするために
で、実際に行っている乾燥調製作業の様子です。
倉庫から、半乾状態(刈取り直後に1回乾燥させた状態)のモミを運び出します。

乾燥調製施設を使わせていただいている所へ運びます。

びっくりするような巨大施設です。
北海道的には普通だそうですが千葉県から見学に来るスタッフは、いつも驚いています。

このフォークリフトが、回転してカゴの中身を出す所も、
「フォークリフトって回転するんだ!」と、驚きます。そういう仕様です・・・・。
で、巨大乾燥機にモミが入っていきます。

1台当たり、鉄コンで6器程度の生モミが入ります・・・・・。
大きすぎて、量がピンときません。
で、時間をかけてモミの水分量を減らす=乾燥させていきます。
某ブログから拝借したこの画像

のように、乾燥が進んでくると「素晴らしい!」という事です。いや~イイですね。さすがです。
この「鋭角的な狭くて高いグラフが、たまりませんね」となるには、解説が必要ですね。
さておき、乾燥がすんでモミ摩り機へ

ここで、モミが外れて玄米の状態へ。
この前後、何度も物理的にフルイにかけたり、光学的に選別したり
色々と工程を 経ていくわけです。
で最終的に、玄米の状態でフレコンにおさまりThe北海道ファームの倉庫に戻ってきます。

この状態で、玄米。食べられると言えば食べられますが、通常は、さらに精米行程へ。
もうひと作業、白米にしてようやく皆さんイメージのお米の状態になります。
収穫からの乾燥調製も、お米の食味を左右する大事な工程です。
この部分は、いつも他の所でお世話になっているので、本当に感謝です。
いろいろな方のご協力があって、The北海道ファームのお米ができています。
さて、今年の新米 どんな味に仕上がったか試食が楽しみです。
2016年10月17日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
田んぼのワラだしは、終わりましたがよりよい田んぼを作るために田んぼの手入れ作業を進めています。

主に来年の春に向けた田んぼの排水性を向上させ、田んぼの乾燥を促すための作業です。

写真の青い作業機、サブソイラという作業機を使い田んぼの土中に溝を掘っています。

土中から上げてみると、こんな大きなナイフ状になっていて
これが土中を走ることで地面に溝状に切り込みを入れていく仕組みです。

ナイフ状の切り込みを入れると同時に 手で持っている「通称 弾丸」を引いていき
土中約30cmの所にパイプ状の水の通り道も 作っていきます。
結果土中において、このナイフ状の切れ込みから、パイプ状の水の通り道が出来て
その水が暗渠排水に流れ込み、排水路に水が落ちていく。
それで、田んぼの排水性が向上して、田んぼの土の乾燥が促進され、田んぼがよく乾くという訳です。

だいたい5~10m間隔くらいで、溝掘り作業をしています。
よく乾く田んぼは少な目に、乾かない田んぼは多目にとか、さじ加減に悩みますが
栗原の場合、迷ったら多めの傾向です。
最近、色々と宣伝していただいて新規でブログを見ていただく方が増えているようで
今回の記事は、???状態の方もいらっしゃると思います。
というか、いま「農家以外は意味不明な記事」とH社員に突っ込まれました。
そうですね。反省します。
より多くの方にThe北海道ファームの田んぼに興味を持っていただくためには、
「田んぼの構造~田んぼは、池ではありません」という記事を作って、
解説していかないといけないと思っています。
次回以降の宿題にさせてください。
「深遠なる田んぼの世界へようこそ。今日からあなたも田んぼ通」シリーズの
連載に向けて準備します。
2016年10月08日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
田んぼの作業が一段落、中古農機具展示会へ行きました。
お目当ての、機械は、状態と値段のバランスが悪くて購入には至らなかったですが、
ついでに、色々見てきました。

大型トラクターが並んでいます。

「FORD」 ブルーがきれいでイイですね。

「JOHN DEERE」 いい色ですね。
単に丸目のレトロなトラクターが好きなだけの趣味の世界。
宝くじに当たったら買うリストに載せておきます。

小型の自走式ロールベーラー。
田んぼのワラだしに使える機械。北海道では希少な小型版。
めぐりあうのが数年早ければ、買ったかもしれない・・・・。

「ホンダ モトラ」
多分ノンレストアのオリジナル状態。希少車ながら破格の安値。
100%趣味で個人的に衝動買いしたくなる1台ですね。う~ん。欲しい・・・。
まぁ、機械の知識は、農家には欠かせない知識ですが、半分趣味のような気もしてきました。
もちろん遊びに行ったわけではないですよ。
運搬車とか、ワラカッターとか、仕事上必要なものを見に行ったんですよ。念のため。
H社員が、うれしそうにソフトクリームを食べていたのもマーケティングの一環です。たぶん。
ちなみに、日高の展示会だったので

来場者駐車場の脇に、馬が放牧中。
なんかすごいぞ!さすが競走馬の産地。
2016年10月08日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
The北海道ファームのお米作りは、真面目だ!と主張しているわけですが、
そのおいしいお米作りに対する真面目さ、愚直さの象徴的な作業がこのワラだし作業。
収穫後の田んぼから、稲穂を外したワラを運び出す作業です。
前回ブログで数千、数万のワラ束を拾う所をご紹介しましたが、
当然、拾い上げるだけでは、終わらないわけで
拾い上げたワラの束を田んぼから運び出さなければいけません。
という事で、ワラを拾って運び出す作業
① 軽トラ作戦

軽トラが、直接田んぼに入って拾ったワラを荷台に放り込んでいき、
荷台がいっぱいになったら、そのまま道路を走ってワラ置き場まで走ります。
一番効率はいいですが、田んぼが車が走れるくらい乾いていないとできません。
② 運搬車作戦

コンバイン改造運搬車にワラを拾い集めます。
キャタピラ仕様なので田んぼが多少湿っていても安全に走れます。
田んぼも傷みにくくいい感じです。

運転手とあいまって雰囲気は、やや怪しいです。
アゼまで運んで来たら、トラックに積み替える作業が必要です。
ただ、「おぉ、調子いいね」と3日間作業をしたら、運搬車が御臨終してしまいました。
内部でミッションがいってしまったようです。修理は、高額かつ部品がないのでほぼ不可能・・・・。
昨年、5万円で購入した機械なので「1日1万のレンタル」と思い、自分を納得させました・・・・。
③ トラクター作戦

トラクターに鉄コンをつけて、

田んぼでワラを拾い集めます。

アゼで、トラックにワラを積みかえて、ワラ置き場に走ります。
結局 作戦①軽トラ作戦と 作戦③トラクター作戦を
田んぼの状態によって使い分けながらワラだし作業を進めていきました。
結果今年は、10月3日にすべての田んぼからワラを出すことができたので
昨年比20日近く早いワラだしの完了です。素晴らしい!
このワラを出すための作業は、ここ数年とてもつらい作業で苦しんできましたが
なんとか、いい方式になってきたような今年です。
何は、ともあれ「ワラだし作業が終わって ホッとした~」というのが本音です。
~追伸~
ミッション破壊で走行不能の運搬車、あげます。
非農家の方、オシャレなガーデンの飾りにどうですか?
農家の方、部品取なら、使えそうですよ。キャタとかきれいだし。
2016年10月04日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
The北海道ファームのお米作りは、真面目だ!と主張しているわけですが、
そのおいしいお米作りに対する真面目さ、愚直さの象徴的な作業がこのワラだし作業。
収穫後の田んぼから、稲穂を外したワラを運び出す作業です。
まず、なぜ収穫後の田んぼからワラを出すのか?という事ですが、
これは、田んぼの中でワラを腐らせると稲の生育に悪影響、肥料の効果が計画どうりに行かないなど、
健全でおいしいお米作りの障害になるからです。
※理由を 説明すると長文になるので詳しくは省略。
とにかく、高品質なお米作りにはワラの搬出は欠かせない作業ですが、
現実的には作業負担が大きすぎて ほとんどの農家では、やりたくてもできない作業です。
でもThe北海道ファームでは、「絶対にワラを出す!」と決めて、この大変なワラだし作業を進めています。
まずは、今年から導入されたコンバインのオプションパーツがこれ。

結束機!
なんと、刈り上げてモミを外した稲わらをヒモで縛ってくれるスーパーパーツ。
仕組みが複雑すぎて、トラブルが頻発していましたが、いい働きをしてくれます。
写真では、赤い矢印で示したところに、結束機で縛られたワラ束が出てきています。
この、結束機を使うとこんなワラ束ができます。

ちょうど、真ん中あたりで縛られています。
コンバインの中に紐でワラを束ねて結ぶという素晴らしいカラクリが仕込まれていますが、
どういう仕組みでこうなるのか、いまいちわかりません・・・・。
で、そのワラ束が稲刈り後の田んぼ一面に落ちている状態になります。

赤矢印で指し示してみました。
だいたい1m~2m間隔で1個落ちているイメージです。
という事は、そう田んぼ一面にこの状態。

たとえば5反田んぼで数百の束が、点々と・・・・・。
The北海道ファームの7・5町の田んぼ全体では、何千、何万のような気がしますが
数えると嫌になるので、数えたくない・・・・・。
とにかくこれを、全部拾い上げるという作業が、ワラだし作業です。
じゃあ、どう拾うのかというと・・・・The手作業!

この写真のように、一つ一つ心を込めて拾います。
数千、数万を手で拾う!想像するだけでもその大変さが解っていただけるかと思います。
で、案の定1日ワラだしをすると、「腰が痛い・・・。」「足が・・・・。」と故障者続出。
ワラを一束拾うのは、たいしたことが無くても何せ数が多い、一日中拾い続けても終わる気がしないくらいなので。
でも、高品質なお米作りには欠かせないので、The北海道ファームでは、
とてもつらい作業になる事が解っていながら、やるんですね。
「いつ終わるか?そんなことは考えてはいけない!まず目の前の一束を拾う。
そうすれば、いつかは確実に終わるから・・・・。まず一束、もう一束・・・。」
「一つ拾えば、終わりが近づく。一つでも多く拾わないと、いつまでも終わらない・・・・。」
精神状態を務めて平坦に保ちながら、少しずつ少しずつしか作業は進んでいきません。
ほとんど修行のような作業・・・・。
稲刈り後の、このワラだし作業、今年から作業方式を見直しましたが、
長いつらい作業であることには、かわりがありません。
でも、このワラだし作業を続けてきたことで 夏の田んぼに実感できる変化が起きているのも
よくわかるので、やっぱり実施しないわけにはいかない作業です。
よい田んぼを目指して、真面目に作業に取り組んでいます。
~次回その2に続く~
2016年09月29日
The北海道ファームの稲刈りは、一応無事に終了いたしました。

稲刈りが済んだ田んぼです。ずいぶん風景が違って見えます。
ただし、落ちている稲わらを見ると気分が重くなるのは、後日説明します・・・・・。
とにかく、稲刈りが終わったのですべての仕事を放り出して午後から休み!です。

という事で、子供を連れて栗山天満宮例大祭へ。
3日で動員20万!(動員数については諸説あり)らしいですが、
それもうなづけるほどの、ものすごい人!人!人!
北海道最大規模の出店数らしいです。確かに駅前から天満宮まで
約1kmにわたり道の両側に出店がびっしり!なかなか関東でもここまでの規模は見られない。

オートバイサーカスという「男はつらいよ」に出てくる興行もある!
もうほとんど伝統芸能というか文化財級の興行だと思います。

ヤマハのRDシリーズのように見えます。レアな旧車ですね。
樽の中をオートバイで走るので、ツインのトルクが有利なんでしょう。と読者を限定する感想を述べます。
ちなみに「くじ引きがしたい!」という事でサーカスは、見ないことに・・・。

子供だましとは、よく言ったもので大人から見ると
「その景品は、ぜったいに出ないだろ~」という商品ねらいでくじ引きに挑戦、
案の定、はずれの残念賞を引きまくる幼児・・・・・・。1回300円。
自分のお小遣いを使い込んでいるから、まぁいいか・・・・。
いつか、「すごいあたりは出ない仕組み」に気が付く日がくるまで、楽しめばいいさ。
そういえば、綿菓子について
「ぼくさ~、綿菓子は袋の模様がちがっても、味はみんな同じって知ってるんだよ」と
ドヤ顔で語ってきました。そこは気が付いているようです・・・。
やっぱり、子供にとって祭りは、魅惑の世界のようです。
栗山の祭りは3日間開かれますが、3日間毎日祭りに行きたいようです。
大人は、疲れるので1回行けば十分なんですけどね・・・・。
なお、The北海道ファームの美白男子H社員は、
地元でもないのに3日間毎日仕事終わりでお祭りに通い、出店で食い倒れていたそうです。
しかも寮の冷蔵庫もお祭りで買った食べ物が満載・・・。楽しそうでいいですね。
2016年09月27日
2016年09月21日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
稲刈りが始まり、はや4日ほど経ちました。今のところ天候もよく、
粒里さんにも色々とご協力いただいて、なんとか順調に進んでいるような気がします。

登熟も まあまあでこのままのペースで稲刈りを進めていきたいところです。
そんな絶賛稲刈り中の田んぼは、意外に日差しが強く日焼けをします。

The北海道ファームの「美白男子」林さんは、日焼け止めが欠かせません。
朝と昼休み1日2回のお肌のお手入れは、重要な作業。

外で作業するときには、このいでたち。やや不審者風です。
※冗談ではないです。本当です。
本人いわく「お肌が弱いタイプ」だそうです・・・・・・。

そんなこんなで稲刈りは、進みます。
で、なぜかこの農繁期に栗原は町内の草刈り当番に当たってしまうという間の悪さ。

田んぼの稲刈りは、スタッフにお任せして、公園で草を刈っていました。
まぁ、草刈りも農家の基本なので手馴れています。
「さすがに上手だね」とやさしい御町内の皆さんにおだてられて、頑張りました。

最後は、刈り取った草を集めてゴミ収集用に袋に詰めるところは、
農家仕様の草刈りでは、しない作業。結構大量の草が出ました。
公園もきれいになったし、町内の知り合いも増えたし、たまにはいいですね。
稲も刈るし、草も刈る。あとは自分の髪の毛を刈ればすっきりします。
2016年09月17日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
いよいよThe北海道ファームの稲刈りが始まりました。
地域の中では、早く始めた感じですが、ななつぼしで水分量23%程度ということで、超刈り時です。
「適期だっ!」

とりあえず天候もよく、田んぼもよく乾いています。

立ち上がりのマシントラブルで時間がかかりましたが、
ようやく順調に刈り取れるようになってきました。このまま調子を上げていきたい所です。

ダンプに刈り取ったモミを移しています。
ダンプとコンバインの位置取りがポイントです。
息が合ったコンビネーションで、仕事がはかどります。

そして、今回の稲刈りのポイントはこれ!
コンバインの後ろの結束機、稲わらを束ねて吐き出す装置です。
刈り取った後に ヒモで結ばれた稲わらの束が落ちています。

この 結束機のセッティングが出なくてトラブルが頻発。
まともに動かない状態で総勢6人のKUBOTAスタッフが入れ替わり立ち代わり
結束機の調整で試行錯誤中。まるで「クボタのワークスチーム」のようです。
結束機自体が「最近、使っているところがない」というようなレアな装備なので、
初期の調整が難しいのは、しょうがないかなという所です。
半日かかって 結束機の調子も出てきたのでなんとか大丈夫でしょう。
さぁ、稲刈りの日々、約1週間の予定。その間は晴れが続きますように祈りつつ作業を進めましょう。
ちなみに 稲刈りをしてもそのあと乾燥→再乾燥→モミすり→精米と手順を踏まないと
食べられるようには、なりません。食べられるようになるのは、もう少し後です。
私、栗原もまだ食べられません。皆様も少々お待ちくださいね。
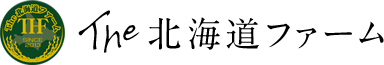











































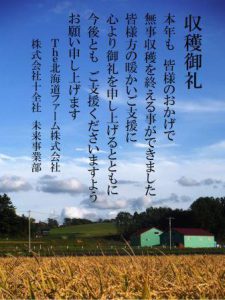











 農場ブログ
農場ブログ