2015年11月20日
何事も勉強が大事。
せっかく東京にいるので、お米の小売店巡り。
目指すは、お米売場!

一般的なスーパーのお米売場。

生産工程を紹介するパネル。工夫してますね。

駅近のスーパー。売り場の半分がパック飯。
精米もほとんど1kg、2kg、1.8kgで売られています。5kgでさえも、少数派。
小家族の時代、駅近スーパーは持ち帰りも徒歩だろうから、
少量パックしか売れないんでしょう。電車で5kgの米を持ち帰るなんてありえないし。
時代の変化を感じます。

有名な高級米が大きくいい売り場を確保していたり。
いろいろ勉強になりますね。

こちらの有名高級スーパーで、発見!

ちょっと写真が悪いですが、
いつもお世話になっている栗山町の杵臼ファームさんのお米。
「杵臼米 特別栽培 ななつぼし」 すごいですね!
はるばる、東京で見つけてしまいました。ちなみに、購入しませんでしたが・・・。
他にも、自然食品の店でお米を見たり。いろいろ勉強になりました。
小規模店では、精米のお米売場がない!パック飯だけ!なんて所もありましたね。
小売りの店頭では、全体としてお米の存在感が薄くなっている感じがします。
たとえば、品ぞろえでいえばお米は5種類くらい、そばは20種以上なんていうのも普通。
なんだか、さびしい限りですが、それも現実マーケットの動向ですね。
結局、あいていた東京滞在中の半日をお米売場めぐりでつぶしてしまった。
真面目すぎるぞ!自分!いや、やっぱり気になるんですよ。お米の販売も。
どんなものがニーズがあるのか、マーケットインの発想は大事です。
生産サイドからも、販売サイドからも、時には消費者サイドからもいろんな見方で
お米の勉強をしていこうと思っています。
~おまけ~
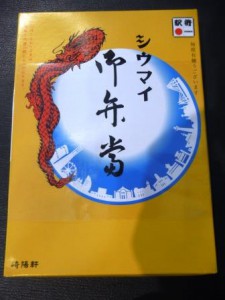
今回のお土産。崎陽軒のシウマイ弁当。ある意味ソウルフード。
北海道では手に入らない、これを買うのも出張の目的。
2015年11月20日
The北海道ファーム、外での農作業はほぼほぼ終了していますが、
この時期から増えてくるのが 研修、会合、見学etc つまりは勉強。


午前6時過ぎの誰もいない新千歳空港から、向かうは東京 六本木。

経営コンサルタント会社の研修に参加します。
「経営戦略」の研修なので、数年の世界経済、日本経済の先行き分析や
そこに向けての取るべき方法などの考え方を 勉強しました。
一般企業対象なので、農業関係者は、多分ひとりだけ。
数百人の参加者の中99%がダークスーツにネクタイのおじさんたちなので、
異様な雰囲気、なんか違和感がありますね。
農家の研修では、全員がスーツ姿というのは、ほぼありえないもので・・・・。

研修が終わって外に出てくると、もう夕方。
一日、講義を聴き続けるとさすがに頭が疲れてきますね。
普段は、一日中経済、経営の話は、しないですし・・。
そのあとは、本社のみなさんと食事に。
お店の名前は、出せませんが、
「南魚沼十日町産コシヒカリ特A、土鍋で炊いた炊き立てごはん」
2合炊きで1800円!くらい という目玉メニューを発見、さっそく注文。
待つこと40分くらい、出てきましたよ。
という事でさっそく試食!完全に仕事モード。
??????
いや、わかりますよ。炊飯器炊きで保温するよりもいいのは。
ややアルデンテ状態に仕上げてあるようですが、表面のべた付き感が・・・・。
その割になべ底焦げてるし・・・・。
水に浸けて、ザルに上げて、この辺の調整が?なのか、あるいは水の特性が?なのか、
40分で出てくるところから判断すると、米とぎや浸水は、事前にしてるだろうから・・・・。
まぁ、いろいろ考えてみますが・・・・うーん。
もしかして炊き方失敗したの?いつもこれ?わからん。
結論は、これなら北海道米をきちんと炊けば、充分勝てる。
お米の味に関しては、好みがあるから言いませんが
「もっと、きちんと炊いてほしい」看板メニューならなおさらです。
他の食事やお酒は、おいしいだけに少々がっかり。
その後は、宿泊地に移動(さすがに六本木ヒルズの高級ホテルには泊まれません)
酔っぱらって電車で移動なんて、ものすごい久しぶり感。なんだか都会を感じました。
でも、やっぱり北海道暮らしの方がイイですね~。
2015年11月17日
田んぼの作業が終わったThe北海道ファームです。
農家の仕事は終了という事で、変身!

精米工場の仕事にチェンジしました。モデルは、H社員。
The北海道ファームで一年間丹精込めて育てたお米を
精米して、パック詰めをする作業のテスト中。

玄米を右のほうの機械を通して白米にします。
白米になったお米を 左の方の色彩選別機を通して、
食味を落とす原因となる米粒や異物が入らないようにしています。
この選別の設定で、お米のグレードが変わる部分です。
もちろん、厳しい選別設定、着色粒の選別強度や白未熟粒の選別強度など
各項目を試しながら、ベスト設定を探ります。

つぎに、厳しい選別を終えたお米をここで2合づつ袋詰して
窒素ガス充てんをして製品に仕上げていきます。
窒素ガスは、お米の食味を落とさないための必須技術です。
この窒素ガスを充てんすることによって、

袋内の酸素濃度を1%以下におさえます。
表示は0.585% やや高い感じですね。もう少し下げたい。
これがお米のおいしさをKEEPする上での重要技術。

続々と製品になったお米が出てきます。

出荷できるように、袋に入れていきます。
1袋に390個入るようです。
と、簡単にご紹介しましたが今後のブログでこの設備の全容を
一つづつ解説していきたいと思います。
あまりにもすごい機械なので、その魅力は語りつくせないのです。
ここ最近は、操作ノウハウの定型化や作業精度を上げるため 試行錯誤しています。
農家の仕事がひと段落した所で、食品工場のラインを稼働させる仕事に華麗に変身。
ラインが順調に稼働するようになったら、ライン工に変身。一人二役は当たり前。
そういえば、試算によると15万個以上の袋詰め作業が待っています。
1時間に400個ペースくらいだから、全部終えるのに・・・375時間!
1日8時間稼働で47日間!一日ひたすらパックの補充と袋詰めの日々・・・。
計算しなければよかった・・・・・。
※なお、写真のお米は実験用にとってあった去年の古米です。
2015年11月12日
The北海道ファームのメイントラックがこちら。

トヨタのダイナ1.5トン積のトラックです。
通称「平ボデー」。ボディではなくボデーです。
1.5トン積みという事で、正直コメの運搬には役不足。
1トンのフレコンという通常のお米の運搬単位だと、1袋しか積めません。
という事で、新車を購入!めでたく納車されました!

今度も、トヨタ。カラーはオレンジ!派手!目立つ!
新車はボディの輝きが違いますね。

積載量は、2.3トン!フレコンで2袋でも余裕の積載量!
しかも、ボディも小さいので小回りもよく聞きます。
これで、仕事がはかどるというものですよ。
では、お披露目を。
じゃん!

もう お判りですね。ハンドパレットでした。

狭い室内での、お米の運搬にはこれが最適!
The北海道ファームのこれからのお米の包装作業で大活躍しそうな新車です。
お後がよろしいようで・・・・・。
2015年11月09日
デジカメのデータが消えたので、記事が作りにくいですが。

The北海道ファームの田んぼにサブソイラでの溝切作業が終わりました。
11月に入って奇跡の晴れ続き!1週間雨がなかったので田んぼが乾いて
トラクターを田んぼに入れての作業ができました。
10月が雨が多かったので、田んぼの作業は、
ワラだしまで無理やり行って終わりかなと思っていましたが何とか溝切までできました。
これで、来春田んぼが順調に乾いてよい状態になる準備ができたはず・・・。
あとは、来春の晴天高温を祈るのみ。来春も田んぼには、しっかり乾いてほしいものです。
これで、雪が降る前の田んぼの作業は本当に完了。なんとかなったことにしましょう。
ほかにも、もみすりをしたり、玄米を収納したり。
あるいは、製品化の加工場の機械を試運転して不足品を手配したり。
冬の準備もいろいろあるのに なかなかすすまない。
そうそう、打ち合わせも多かった。色々問題が勃発しているわけです。
農家の作業が終了でも、製品化の作業はこれからスタート。
お米が無事に収穫できただけでは、The北海道ファームの仕事の半分が終わっただけ。
収穫したお米を製品化して、お客様にお届けして、そこで初めて仕事の終わり。
まだまだ道半ば、やるべきことは多そうです。
2015年11月09日
The北海道ファームの近所でも紅葉がきれいな時期になりました。

田んぼの裏山もきれいですね。

赤い紅葉は、またいいものです・・・・・。
突然の紅葉の話題で・・・・・・現実逃避です。
ええそうです!やってしまいましたよ。
デジカメのデータ、謎の消去!
いつものようにデジカメからカードを抜いて、PCに入れたら
「開けません」とかなんとか。デジカメでは画像確認できるのに・・・。
なんだ、なんだ、といじっていたら、データが半分消えました。
本当にわけがわからない・・・・。
なぜか10月17日以前の画像はカード内にデータが残っているのに
この3週間ほどの分だけデータが消去。そんな事ってありですか。
全消去ならまだわかりますが、ゴミ箱にも消去データが見当たらないし。
現象から判断するに、データを選択して消去しないとそうはならないはずですが・・・・。
まいりましたね・・・・・。作業記録写真もあったんですが。
あぁ、紅葉がきれいだな・・・。
2015年11月05日
ここ数日、近所のもみすり工場にこもっています。

巨大施設なので、まさに工場。
大きな機械の間を コンベアでお米が動いていきます。
The北海道ファームのお米ですが、
刈取りをしただけでは、もちろん食べられる状態ではありません。
今現在の工程としては、
刈取り~乾燥1回目~乾燥2回目~もみすり、まで進んでいます。
お米の状態としては玄米です。
さらにこの後の工程で、精米~袋詰めと進んでいきます。
ここまで終わって、白米。いわゆる食べられるお米です。
なお、工程の途中でお米の選別が行われていますよ。
工程の説明は別に詳しくご紹介するとして、
今現在のもみすり作業、一日中工場にこもっているので結構つらいです。
というのも、自分で作業するわけではなく機械が作業をしているので、
とにかくヒマ。いや、訂正、待機時間が長いんです。
もみすりの機械、ラインが動いているときには、

この操作パネルの表示を監視しているか、

このパネルで、もみすり収量の量を確認して
1時間に1回くらい、仕上がった玄米を入れるフレコン袋を交換する。
そんな感じが1日中続きます。
もちろん、ごくまれに機械トラブルが発生するので、全体の作動も監視していますが
基本的には、ノントラブルで作動するので、あんまりやることがないです。
でも、その場を離れることはできないという状態。
なんだか時間を持て余すので、本を持ち込んで勉強中。

二宮金次郎以来の 農作業+読書。
結構、機械音とお米の動く音で騒音がすごいのでいまいち頭に入りません。
PC持ち込んで仕事をするにも、少々ほこりも舞っているのでよくないし。
The北海道ファームの7.5町分の米で1週間くらいの作業になります。
なんだか、お米って刈取りしてから食べられるようになるまでの作業も
時間がかかって大変だと、あらためて思っています。
そういえば、自分で作った今年のお米まだ試食もしていない・・・・。
やっと食べられる状態になってきたので、そろそろ食べてみようかな。
2015年10月31日
心土破砕(しんどはさい)
なんだかすごく意味深な単語に思えます。心の土を破砕するんですよ。
心機一転、古いこだわりの心を捨てて頑張りますみたいな。そんなことないか。
本当は、田んぼでの秋作業の一つです。
「サブをかける」と言ったりもします。

この作業。ワラだしの終わった田んぼに、サブソイラという作業機で
地面に切り込みを入れ、同時に土中に空間を作る作業です。
地面に切り込みを入れることによって、田んぼの地下40-50cmにある暗渠という
排水設備に水が流れていきやすくなります。
この作業をすることにより、田んぼの透水性の向上、排水性の向上を見込めます。
「秋のサブは、春乾く。春のサブは秋乾く」 そんな風に言われています。
つまり、秋稲刈り後にサブを入れることで、春の融雪期に田んぼの排水がよく
雪解け水が排水されやすく、田んぼがよく乾く。
春の田起こし前にサブを入れることで、秋の稲刈り前の田んぼの水を抜く時期に
水が抜けやすく、田んぼが乾くという事をいっています。
そう、この作業は半年先の春の田んぼ作業を考えて行う作業なんですよ。
いま、きちんと田んぼの手入れをしておくと、春にいい状態になる!
何事も先を見据えて、今大変でも準備しておく。
田んぼだけでないすべてに共通ですね。
目先の事だけ考えていてもだめなんです。将来どうなるかが大事。
もとい、このサブソイラの作業。
地面に切り込みを入れていくという事でポイントは、深さと位置。

深さは、地面に切り込みを入れていく深さが暗渠付近まで到達し、
かつ暗渠のパイプ自体には到達しない深さを目指す。
地下約35~45cmを目安という事で切り込みに10cmごとにメモリを付けた棒を差し込んで
切り込みの深さを確認しつつ、作業を進めます。
※田んぼにより深さは異なります。暗渠の敷設深度にもよります。

溝を切る位置も、土中の暗渠排水がどういう配置かを考えながら、
どう溝を切ると暗渠につながるか、あるいは、田んぼの表面のどこに水がたまりやすいか
なんてことを考えて作業をします。
農家の世界は、「勘と経験」とよく言われますが
この心土破砕の作業でも、理論を勉強して現実に即して作業を進めています。
理論的に説明がつく、きちんと研究された栽培方法は基本として大事。
そのうえで、いわゆる「勘と経験」の世界が出てくると思っています。
最初から「勘と経験」だけを頼って、科学的に勉強をしないのはNGで。
農家の先輩方も、「勘と経験」といいながら、実はとてもよく勉強しています。
品種の事、作業の事、資材の事、機械の事、新しい農法 etcすごい知識量。
「勘と経験」を働かせるにも、勉強=情報のインプットは絶対必要ですね。
「今年は天気がいいから豊作だ~」 この言葉は、ある意味ウソ。
豊作には、豊作になる理由がある。不作には不作になる理由がある。
絶対に、天気だけが理由ではないと思います。
農業は、単なるお天気頼み、神頼みの世界ではないですよね。
最大限の科学的農業+αの神頼みだと思います。
あぁ農業、勉強すること限りなく。楽しいな。
心土破砕からずいぶん話がズレました・・・・。
2015年10月30日
The北海道ファームの今年の秋作業で負担が大きい作業、ワラだしが終わりました。

ワラのロールがなくなってすっきりとした田んぼ。

ワラがない状態でしっかりと地面が乾いてほしいものです。
でも、ワラだし作業でかなり地面に無理させてしまい
入り口付近の状態は、悪い状態になってしまった・・・・。
本当に雨に泣かされた今年のワラだし作業。
作業機械の不調にも泣かされました。

こんな作業や、

こんな作業。
一般的な農家の方が取らない大変な作業の数々。
おいしいお米作りに欠かせないとはいえ、人力に頼った大変な作業でした。
雪が降る前に 完了してよかったよかった。
スタッフの皆さんの頑張りは来年のお米作りによい結果として答えが返ってきます。
と、無事完了でほっと胸をなでおろしつつも
実際には、ワラだし作業には反省事項が山ほどありますね。
作業タイミングや機械の稼働時間の問題からのボトルネックの発生とか・・・・。
一つ一つ問題点を洗い出して改善していかないと毎年大変な事になるし。
それは、ワラだし作業についてだけでは、ないんですけどね。
The北海道ファーム、まだまだ改善するところがいっぱいです。
2015年10月25日

10月25日 The北海道ファーム 雪が舞い始めました・・・・・。
昨日あわててスタッドレスタイヤにしたけど、外の仕事がたくさん残っている・・・・・。
根雪になる前に 冬準備を進めていかないと。
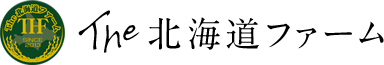







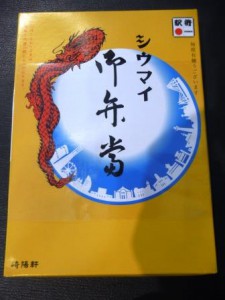






























 農場ブログ
農場ブログ