2016年08月17日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
8月に入ってわりと晴れた日がおおく仕事がはかどっていました。

が、ここにきて台風が北海道上陸を目指して進行中です。

The北海道ファームのある北海道栗山町も、夜半過ぎから雨が強くなってきました。
農場周辺も、時には視界が効かないくらいの局地的大雨。
となると、当然。

田んぼは、満水状態。意図しない入水です。
秋の稲刈りに向けて、田んぼの水を抜く時期が来ているので、
この雨が終わったらだんだんと水を抜いていこうかなと思っています。
そう、稲の生育と天候を見ながらの水管理はお米作りの重要事項です。
そうは言っても田んぼも無制限に水をためられるわけではないので、
台風のような局地的な大雨に見舞われると、

小さい排水溝は、すぐに水位が上がってきます。
深さ40cm程度のU時溝があふれています。
そうなると、下流で水を集める大きめの排水溝も大変なことに。

農場の敷地内を通る排水溝ですが、幅1m程度の排水溝がすごいことに・・・。
矢印で示した排水管の出口は、いつもは水面の上50cm以上から
滝のように水が落ち込んでいる場所なんですが、今日はほぼ水没中。
それだけ、水位が高くなっているというわけで・・・。
これは、下手に近づいたら流されるな。

空いた畑で、遊びで種まきをしたダイコン。
水没していますが・・・・・。大丈夫?じゃないような・・・・。
畝を立てた所が3本、かろうじて水面から顔を出していますが、島のようになっちゃった・・・。
水耕栽培の実験ではないんですが・・・・。うーん。どうなるものか?
こういう豪雨の時にウロウロしていると、用水路に流されたりするんだろうなと思います。
毎年、台風に時期に「年寄りが用水路に流される事故」がニュースになりますが、
なんとなく気持ちは、解るような。台風の非日常感にワクワクする気分。
まぁ余計なことしないで、明日、台風が去るまでおとなしく他の事をしよう。
事務の作業とか、計画書の作成とか、雨でもやることはあるわけで。
2016年08月16日
The北海道ファームのある北海道栗山町。
お盆も終わり、秋の気配が感じられるようになりました。
農業の世界でも、町内ほとんどの畑で小麦の収穫は、終わったようです。

そういえば、「新小麦」とは、言いませんね。
「新米」「新そば」は、言いますが。
小麦の場合は、その年獲れた事にあまり意味がないんでしょうか?
「新小麦のパスタ」とか「新小麦のパン」というのは、見かけませんね。
※今、調べたら小麦は、熟成しないと粉の性質が利用しにくいとか・・・。深い世界があるみたいです。
そんな小麦の収穫が終わり、お盆前後から本格化するのがタマネギの収穫です。

ご近所の畑でもだいぶタマネギが育ってきました。
今年は雨が多く難渋しているそうですが、それでも収穫の時期になってきました。

天気がよいなか広大な畑での収穫作業です。
規模が大きいので(1枚の畑で1ヘクタールとか)もちろん機械での収穫作業です。

道端にタマネギがおいてありました。
写真ではわかりにくいですが、3段積で5m近い高さです。

こんな感じでタマネギがぎっしり詰まっています。
スーパーの店頭では見ることがない、ものすごい量です。
う~ん。すごい量。これで「ちょっと収穫してみた」という程度だそうで、
北海道農業はダイナミック!まぁ家庭菜園と比べてはいけませんよね。
「葉っぱごと、3個とか束ねて新タマネギと売っているのを見かけない」と言う人がいましたが
この規模の畑と収穫量では、そういう製品を作らないのも解る気がします・・・・。
ちなみに、栗原はタマネギにも「品種がある」というのを北海道に来て初めて知りました。
いや「黄色いな~」「赤いのもあるな」くらいは、知っていましたが、実は北海道では
主なものだけで数十種は、あるようで・・・・。知らなかった。
「きたこがね」「ブラウンベア」「カムイ」「オホーツク」等々、いろいろあります。
早生、晩生の栽培方法の違いや、味や特性もそれぞれ違うようですが・・・・正直、今でもわからない・・・。
小売店の店頭でも、なかなか品種までは、書いていないと思います。
それでもやはり!栗山町名産「さらさらレッド」も忘れてはいけませんね。
血液さらさら 健康機能性の高さがウリですよ~。一度お試しください。
生産量が少なくレア品種です。入手方法など詳しくはこちらで → http://sarasara-red.com/
ちなみに、ご近所のT氏は「ベガス」という品種が好きらしい。
その理由が「一攫千金で儲かりそうだから・・・。」 では、また次回、農業の扉で。
2016年08月14日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
夏ですね。町内のひまわり畑です。

山裾までずっと広がっているような広大な畑です。
きれいですね・・・・・。
つい作物としてのひまわりについて考えてしまいますが・・・・。苦笑。
8月も半ばになり、お米作りもいよいよ終盤に差し掛かってきました。
7月から8月初め、深水管理終了~中干しと水の管理に奔走していましたが、
今は、水の管理もやや落ち着いて水深3cm~地面が見える位までの間で調整しています。

もちろん朝夕の見回りと、こまめな手入れは欠かさずにやっています。
朝夕の見回り時に、ついでに草刈りをしたり、
毎日少しづつ作業をする方が、体力的な消耗が少ないような気がします。

こんな感じの田んぼの状態です。

近づいてみると、穂が出そろって、早い所ではやや垂れてきました。

色味が、おかしいのはカメラとPCのモニターの調子だと思います。
稲もここまで生育が進んでくると、今年のThe北海道ファームの稲の傾向が見えてきます
去年に比較して、草丈が10cmは低く、横幅も小さ目、全体的に「小さくできた」と思います。
肝心のお米としての、出来上がりはこれからどう稲穂が仕上がっていくかにもよるので
まだ、「こんな感じ」とは言えないわけですが、今のところ順調にきていると思います。
「小さくできて、順調なのか?」そうお感じになるかもしれません。
じつは、小さくできるのは想定のうち、収量が少なくなることも想定内です。
後は、味的な仕上がりがどうなるか?今までよりさらに食味が上がるはずなんです。
仕上がりが、楽しみですね。
2016年08月13日
今回は、非常に対象が限られた内容ですが、栗原が感動したので暴走します。
先日から、田んぼの管理と並行して農場の環境整備でチェンソーを使って伐採作業をしています。
そんな、チェンソー作業の重要なポイントが目立てです。
「目立てなくして チェンソーなし」それくらい大事です。
作業の効率や安全にも関わる、実際に切るよりも大事と言っても過言ではないでしょう。

棒やすりを使って、半日に1回は目立てをしていましたが、これが難しい作業。
チェンソーの切れ味を左右しますが、悲しいかな上手にできません。
そのため、チェンソーの切れ味が悪く1本の木を切るのに時間がかかってしまいます。
そこで、物は試し半信半疑で購入したこの道具!

チェンソー目立て機!

こんな感じで、チェンソーの刃を目立てしていきます。
高速で回転する棒ヤスリを、チェンソーの刃に当てて目立てをします。
刃1か所を数秒でOKな超早業!研ぎ角30度も正確にKEEP!
これは、すごい道具な気配。

おぉ~!いい刃ができています。
手で触るだけで切れそうです。
さらに50コマのチェーンの目立てが わずか数分で終了!
手作業の数倍の早さ!しかも仕上げがきれい。
早速、伐採で試し切りをしてみたら、素晴らしい切れ味!
切れてくる木くずも全然違う!いい状態の刃でこそできる木くずの感じ!
今までの手作業での目立ては、なんだったんだ・・・・・。あんなのは目立てではなかった・・・・。
これは、いい道具!感動した!
目立て時間も短縮!鋭い切れ味で伐採作業もスピードアップ!仕事がはかどる!
チェンソーの目立てが、きちんとできるプロ級の人なら棒ヤスリで目立てをすればいいのでしょうが
チェンソー初心者には、この目立て機はとってもgood!すごくいい!
という事で、ブログ読者の大半を置き去りにして一人で感動しています。
この感動を書かずには、いられない!
この感動を共有できるのは、林さん、あなただけです!多分・・・。
去年の薪づくりの苦労は、なんだったのかと疑問に思うこのスピード感!実感してください。
ファームのチェンソーが生まれ変わったかのような感覚になります。
チェンソー目立て機が、出張からの帰りを待っていますよ。
2016年08月10日
ここ数日、The北海道ファームの敷地で伐採作業をしています。
作業的には、農業というよりも林業というか造園業というか、
けっこう本格的に作業をしています。

こんな感じで、手入れされないで木が生い茂ってしまった林があります。
下草を、除草剤を使い枯らしたので次はこの木々を整理して環境を整えていく作業です。

林式でチェンソー2台方式で、作業をします。
確かに、2台のチェンソーを交換しながら使うと、時間のロスなく作業がはかどります。
2台を交互に使う事でチェンソーにも負担が少ないような感じです。

安全第一で、伐採作業を進めていきます。

結構な大木も、このとおり。
直径30cmクラスの木をどんどん伐り倒して、地面に倒したら、扱いやすい様に細かく切り分けます
チェンソー無しでは、できない作業ですね。

いい感じで、伐採作業が進んできました。
状態が悪い木を切り倒して、残す木は枝を整えていきます。
枝を整える作業は、センスが問われる作業です。
造園屋さんに「枝を整える場合、今すぐに見栄えが良くなるように切るのか?
木が成長した時に見栄えがよくなるように切るのか?」聞いたことがあります。
「それは、庭の主の要望次第。」と言われてしまいました。
栗原の場合は、「数年は手入れしないで済むように」という感じで
やや切りすぎる傾向があると自覚していますがどうでしょう。

という栗原の切り方なので、迷ったら切る。
どんどん伐採してしまいます。
あとで総合プロデューサーから「切りすぎ!」と言われるかもしれません・・。

こんな太い木も切ってしまう。
樹齢は意外に20年くらい。成長が早い木なんでしょう。
あっ、隣の木と近すぎて悪影響だったから切ったんですよ。
一応、全体の木の配置など考えています。適当ではないです。

こんな感じで、いい景色になってきました。
これで、雪景色になれば「山まで続く一面の雪原に印象的な木」という
風景が出来上がると考えているんですが、どうでしょうか?
この際「栗山景観フォトコンテスト入賞」を目指せる景色を作りたい!
伐採作業は、短時間で景色が変わる面白い作業です。
体力的には、ちょっとつらい部分もありますが安全第一で作業中です。

ということで、木こりスタイルでハイポーズ。
2016年08月08日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

倉庫から出てくる謎の物体。
肥料等を散布するときにトラクターに取り付けて使うブロードキャスタという作業機です。
実は、春に使ったままで洗浄しないで、そのままにしてありました・・・。
本来、使い終わったらさっさと水洗いして油をさして保管するべき機械なんですが、
水を使うのが寒かったり、作業に終われたり、ついつい後回しというか、いけませんね。
ということで、いつもより念入りに洗浄作業をします。

肥料が、付着したままだと肥料が水分を吸って固体化して機械を詰まらせたり
サビさせてしまったり、最悪使えなくなってしまうという・・・。

まずい!少しサビが出ています。
念のため、分解して清掃してみましょうか。

意外と分解しやすくできていました。
農機具は、掃除などメンテナンスのしやすさも重要なポイントですね。
メンテナンスを丁寧にしておけば、機械は正常に動くし、寿命も延びる。
という事は、正確な作業と機械費用の削減に結び付くわけです。
ついでに。こちらも整備をします。

トラクターのロータリー。田畑を耕すための作業機です。
中を覗き込むと、たくさんの回転刃がついています。
これが、回転しながら土を耕していくわけです。

土の中で作業をするので、泥だらけ。ブロードキャスタを水洗いしたついでにこちらも泥を落とします。
なお「土が乾いてないのに無理やり作業したな~」と、言うプロのつっこみは禁止です・・。
そのあと、少々ボルトが硬くて苦戦しましたが何とか刃を取り外しました。

見事に折れてますね。
土中の石などの障害物に当たったのかもしれません。

こちらも、結構なすり減り方。
見事なクビレができています。こうなると、上のように折れてしまうのも時間の問題。
本来は、全部の刃(数十枚!)を交換するといいのでしょうが、
今回は予算の都合もあって1番外側の4枚を交換しました。
それでも、ロータリー幅の端まできれいに起こせるようになるはずです。
で、交換で取り外したこの刃をどうすればいいのか、いつも悩みます。
この刃が、自分の身をすり減らして田畑を耕してくれていたのかと思うと
「用済みなので、捨てる。」と割り切りにくい気分になるんですよね。
なんというか、ありがたいというか、粗末にできないというか。
以前取り外した刃も なんとなく、取ってあります・・・。
さて、メンテナンスもしたし次回もこの機械が活躍してくれることでしょう。
機械の使用後の後片付けと言いながら、実は次回の準備作業ですね。
片づけ兼メンテナンスがきちんとできていないと 次回作業が修理から始まってしまう・・・。
ちなみに社内的には、その現象を「トラップ」と呼んでいます。
栗原が機械を使いっぱなしにして、次に使う時に機械が不調で使えない場合、
それは「くりはらトラップ」そう、ワナを仕掛けたな!と怒られるわけです。
そりゃそうですよね。作業ができなくなるわけですから・・・。
トラップ厳禁!はThe北海道ファームの掟です。片づけは次の作業の始まりです。
2016年08月05日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。

久しぶりのいい天気。
毎日このくらい晴れていると、中干しもうまくいくはずなんですが、
稲の生育状況が、田んぼから水を抜いて中干しを続けることを許さないという。
「もう、水をくれないと困る!」稲が言っているようなので、中干しは順次終了です。
そんな、中干しの最中で行う恒例の苦行がこの作業。

そう、ヒエ取り作業です。
なんと、真面目な作業でしょう。
上の田んぼの写真では、判別が難しいですが田んぼの中にヒエが頭を出しています。
アゼからみて「あそこにヒエの頭が出てるな~」という所まで、
田んぼの中に入って、泥に足を取られつつ歩いていきます。
稲を踏んだりしない様に、かき分けて進んでいきます。

ありました。
ずいぶん実=種をつけています。
この種が問題になるので、田んぼに入ってヒエを抜いてくる作業をしています。
いま田んぼに生えているヒエをそのままにしておくと、とうぜん種が成熟して
最後には、田んぼにヒエの種がばらまかれてしまう訳です。
そうすると、来年以降ヒエの生育条件に合うと田んぼからヒエが続々と生えてきて
稲の生育を阻害し、さらにたくさんのヒエの種がばらまかれてしまう・・・。
これが、年々続いてしまうと田んぼがヒエだらけになってしまうヒエ増殖の悪循環になります。
それがまずいからこそ、毎年中干しの時期には、大変でもヒエ取りに入るようにしています。
「今の努力が、来年変わってくる。」
そう信じて作業を続けていたら、ヒエ取り開始から数年たった今年は、ヒエの発生が減ってきました。
※たまたま気候のせいかもしれないですが、そういう事にしておきます。

1枚の田んぼで、結構とることができました。
放置した場合、これだけの量のヒエの種がばらまかれたと考えると、ゾッとしますね。
ヒエを取りに入ってみると、

たいてい、こんな感じで稲の株と一体化していました。
※右半分 やや茎が赤いのがヒエの茎です。
今年のヒエのほとんどは、水田から、ポツンと生えている感じでは、ありません。
と、いう事は育苗時に苗と一緒に育ったとも推測されます。
育苗段階でのヒエの種子混入も田んぼにヒエが生える原因かもしれません。
ヒエが生えるという、一つの現象を取ってみても恐らく原因が複数あり、対策も複数になってきます。
「これをやったら解決」そう単純にいかない、奥が深いところも農業の魅力じゃないかなと思います。
2016年08月02日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
深水を終了して、田んぼから水を抜きました。
そのまま、田んぼ中の地面が乾くように数日間水をいれない本年2回目の中干しに入りました。
田んぼに水を入れないことで、普段水中にある稲の根元まで空気に触れ
稲の根を含めて活性が上がる効果があります。

こんな感じで、稲が根元まで空気中に出ています。
深水管理で腰まで水につかっていた稲が
体全体で酸素を吸いこんで、一息ついているわけです。
健康体の稲を作るためには、やっておきたい作業の一つです。
同時に、田んぼに地面を地割れができる位まで乾燥させます。

約1cm程度の地割れで、稲の根が切れないくらいが理想的です
この地割れを入れておくと、秋に稲刈りに向けて田んぼの水を抜く時に
地割れで水が抜けやすくなるので、田んぼの地面の乾燥を促進する効果が期待できます。
田んぼの地面を 乾燥させる目的は、土質の件など色々ありますが、
メインは、大型のコンバインが支障なく走れるようにすることです。
田んぼがドロドロの沼地状だと、さすがにコンバインも行動不能になりかねません。
重量が3トン~4トンもあるコンバインがモミを満載して田んぼを走り回るので、
地面が硬くないと、沈み込んだり掘り返したり田んぼを痛めてしまいます。
そのため、ここで稲刈り時に田んぼの地面が乾燥するように、地割れを入れておきたいわけです。
教科書どうり、理想的な事を狙って中干しをしているものの
実は、中干しを初めて雨、雨、豪雨、曇り・・・・・・・。ぜんぜん乾きません。
水は、抜いてあるものの地面はしっかり水分を保持。ドロ状です。

そんな天気で数日間。
もう、稲の穂が出てきてしまいました。

順々に穂が出ている田んぼが増えてきます。
穂が出てくると、花が咲き、この時期には稲が水を欲するので
中干し終了で、田んぼに水を入れなければいけません。
ちなみにこの時期の水を「花水」と風流な表現をします。いい表現です。
雨続きの天気の兼ね合いもあって、田んぼの地面を乾燥させる事ができないまま中干し終了へ。
稲刈り前の時期に晴れが続けば、地面に地割れが無くても乾くので問題はないんですが・・・。
雨が続くと、「あの時、地面に地割れが来るまで干しておけば・・・・」という事になるかもしれません。
ただ、穂を出してきた稲が水を欲するのも健康な稲作り上、
無視できないので生育を見ながら、順番に入水していくことになります。
ぎりぎりまで入水を待ちたい地割れさせたい!
稲は水をくれと言っている! 悩みます。
2016年07月31日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
ここ数日、天候が大荒れで参っています。
畑より田んぼの方が天気の影響は少ないとはいえ、強風は稲にもよくない影響が出がちです。
そんななか、稲の保護のために田んぼに深く水を張る時期がすぎてきたので
順番に田んぼの水を排出し始めています。

大量の水が田んぼから排水溝へ流れていきます。

あっちでも。

こっちでも。
と、大量の水を排水溝に流し込んでいくと・・・・・。

まずい。排水溝で洪水が発生!
U字溝の高さを 超えて土手を削っていきかねない水量になっています。
う~ん。水を流し過ぎたか・・・・。
という事になるので、各田んぼの排水口を調整していっぺんに水が流れていかない様にします。

このぐらいの水量なら、まぁ何とかいいでしょう。
排水溝はThe北海道ファームから、よその家を通っていくので
下流の方まで水量を確認しないといけません。
The北海道ファームが一斉に水を流したせいで、下流の畑に水が流れ込んで大洪水!
作物が台無し!なんてこともあり得ます。
それは、やっぱりまずいでしょう。気配り、目配り大事な所です。
このいっぺんに田んぼの水を落としていく作業をすると、
「田んぼって、ものすごい量の水がはいっているんだな~」と思います。
難しくいうと、「農業の多面的機能の、国土の保全機能、水田のかん養機能」を実感する瞬間です。
たまには、難しい表現を使用してみたかっただけですが、都市住民の皆さんには、
???な文章のかもしれないので、解説は、以下のHPを参照で。
参考HP 農林水産省 農業の多面的機能とは
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_about/cyusan/tamen/index.html
それで、この一斉に落水するときに、以前の溝切作業が生きてくるわけです。

この作業ですね。
この溝切作業の結果できてきた溝が、落水の時にはこの様子。

水深が下がってきて、最後に溝切作業で掘った溝を伝って水が出てきます。
そうすると、田んぼからきれいに水が抜けていく・・・・というわけです。
そう理想どおりにはいきませんが、それでも溝がある方がいいのは、間違いないです。
こうやって、深水から田んぼの水を抜いて、ある程度地面が乾くまで2回目の中干し作業へと
続いていきますが、稲の生育タイミングが長時間の中干しを許さない状況になりつつある・・・・。
この辺の1日2日のタイミングの読みと、その時の天候の状態があるので、
「いつ中干しをやめて水を入れるか」非常に悩む時期なわけです。
一人で悩んでいてもダメなので、近所の大先輩方をつかまえて
「中干ししてますか?」「水入れますか?」「稲の生育は?」と
皆さんの田んぼを見せてもらいながら、聞いて回って余計に悩む悪循環。
田んぼによって環境が違うから、当たり前なんですが・・・・。
「そんなに悩まなくても大丈夫。あんまり悩むとハゲるよ~」と言われています。
そう言われても、悩むものは悩みます。
だいたい、栗原は3代続く由緒正しいハゲの家系だ!目指せ!スキンヘッドの農家!
2016年07月28日
2016モンドセレクション金賞受賞の「北海道水芭蕉米」を作っている
The北海道ファームです。→詳しくはこちら 真面目にお米を作っています。
北海道栗山町から農業の世界をご紹介するこのコーナー。
久しぶりの記事になってしまいました。
The北海道ファームのある栗山町では、7月も半ばをすぎて早くも麦の収穫が始まりました。
いま収穫が始まったのは、秋に種をまいて雪の下で一冬越した秋まき小麦です。
この後、春に種まきをした春小麦の収穫にうつっていきます。
北海道に来るまで、小麦畑も見たことがなかったし、
秋まき、春まきの2種類の栽培方法があるのも知らなかったです。
「都会のみなさん、知ってましたか?」
ちなみに品種も色々あって、小麦粉にしたときの性質が違って使い道もそれぞれ違うとか。
小麦一つとっても知らないことだらけでした。
正直、パンやうどんで「国産小麦使用」と書いてあると、おいしいのかなくらいの感じでした。
そんな、僕の不勉強な話はさておき。

広い麦畑を大型のコンバインで一気に刈り取っていく様子は
北海道ならではの風景だと思います。

山の上まで一面の麦畑という風景もいい風景です。
この風景を眺めるだけでも、北海道に来る価値があると思います。
※なお斜面の畑は作業が大変という農家の感覚は、この際考慮していません。
こちらの、畑でも収穫作業中。

写真で見るとサイズ感がよくわからないコンバインですが、

前に停めてある2tトラックと比較すると、その巨大さがよくわかります。

コンバインの運転席に乗せてもらいました。
感覚的には、2階のベランダから下を見下ろしているくらいの感じです。
1度に刈り取る幅は4.5mということで、車がすれ違えるような道路の幅と同じくらいですかね。
畑の中で作業する限りは、大きい方が楽ということでしたが、
畑から畑へ移動するときに、一般の道路を走るときは気を使うそうです。
僕が、運転したら交通標識を倒したり、ガードレールを壊したりしそうですね。
ここ栗山町では、このように小麦の収穫が進んでいますが、
僕が、「すごいですね~」「大きいですね~」と言っていたら
「帯広とか北見とかは、こんなもんではないよ。もっと巨大な畑、巨大な機械だよ」
と、言われてしまいました。興味本位で1回見に行ってみたいものです。
。
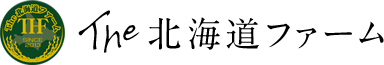



























































 農場ブログ
農場ブログ